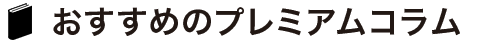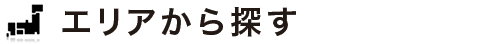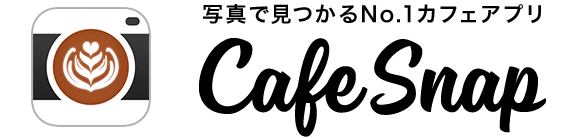ティーマスターに聞く、紅茶の基礎知識(Vol.3)
紅茶とチャイの店、chai breakのオーナー、水野学さんにお話をお伺いしているプレアミアムコラム。
Vol.3はティーマスタ―の水野さんに聞いた“紅茶の基礎知識”。緑茶と紅茶の違い、紅茶づくりの工程、chai breakが大事にしている“産地や季節の特徴が現れる”紅茶とは……?
-

- 紅茶と緑茶の境界線とは
-
- 大井
- ここからは紅茶のお話を伺っていきます。日本にはお茶の文化がありますが、そもそも紅茶と緑茶はどう違いますか。
- 水野さん
- 紅茶と緑茶の違いは実はそんなになくて、一番違うのは“飲む人の意識”でしょうか。紅茶と緑茶を別なものと考えているのは、わりと日本特有なのかなと思います。日本では緑茶屋さんで紅茶を扱わないし、紅茶屋さんで緑茶は扱わないですよね。でも海外では緑茶も紅茶も並列して"tea"として出されていて、扱い方もなんら変わりはありません。実際、生産者の意識も同じで、例えばインドのダージリンに行くと紅茶も緑茶も両方作っています。
- 大井
- そうなんですね!
- 水野さん
- 紅茶と緑茶がどう違うのかと言えば、紅茶は収穫後に茶葉を揉んで発酵させる工程がありますが、緑茶にはそれがありません。なので、そういう意味では緑茶(不発酵茶)と発酵茶は明確に違いますが、発酵茶の中で「半発酵」と言われる烏龍茶と、「完全発酵」と言われる紅茶との境目は実はあいまいだったりします。
製茶における発酵度合は茶葉に合わせてそれぞれ違うので、どこまでが烏龍茶でどこからが紅茶という明確な境目はないですし、例えば紅茶といっても一般の方が見たら「これって紅茶なの?」と思うものもたくさんあります。
お茶の世界に入るとその境界はわりとどうでもよくなって、紅茶も緑茶もそんなに分けて考える必要はないのかなと思います。それに生産者とお話すると緑茶も紅茶も「いいお茶を作るための原理原則は一緒」とよく聞きます。もちろん製造工程は違いますが、「どうしたら美味しいお茶が作れるのか」という考え方は変わらないんです。

- 紅茶づくりの工程
-
- 大井
- 茶葉を収穫したあと、どのように紅茶になっていくのか、工程を教えていただけますか?
- 水野さん
- 紅茶は葉っぱの中に含まれる酸化酵素を空気に触れさせることで発酵という変化が生じます。その発酵は味噌や醤油の発酵とはちょっと違って酸化発酵。厳密には葉っぱの中の酸化酵素によってカテキンが酸素と結合することで、紅茶特有の色や味・香りが出てきます。
紅茶は茶葉を収穫した後、24時間以内にできるのですが、まず半日くらいしおらせて、その後に揉みます。摘んだ直後の茶葉は張りがあるので、それを一度しおらせることで均一に茶葉を揉めるようになります。
均一に揉めないと何が困るかというと、部分的に傷がついたりする。そうするとそこから酸化発酵が始まって均一な発酵ができなくなります。なので、バランス良く発酵させるために一度しおらせて、それから茶葉を揉み、茶葉のジュースを出して空気に触れさせ、お茶特有の味や香りを引き出したら、それを乾燥させる。単純に言うとそういう工程です。
- 大井
- 紅茶はどんな国で作られているのでしょうか?
- 水野さん
- インドが一番多く、ケニア、スリランカなどが主要な生産国です。
- 産地や季節の特徴が現れる紅茶を厳選
-
- 大井
- 様々な国がある中で、chai breakではどんな国の紅茶を扱っていますか。
- 水野さん
- その土地や産地、季節の特徴が表れている紅茶を扱っています。どこかの産地に特定しているわけではないのですが、どんな場所でどんな人がどのようにこだわって作っているかは重要なので、そこを重視すると必然的にいま扱っているインドとスリランカ、この2つの国の産地に集約されています。
ケニアはCTCという製法で作っていて、生産量は多いのですが、わりと紅茶の特徴が画一的になりやすく産地の個性が出にくいんですね。生産ラインもオートメーション化しているところが多く、香りを出すための発酵時間もその茶葉に合わせて調整するというよりも、ラインの中に入れて決まった時間、発酵させているところが多いです。それは大量生産のための方法で、その土地で作られた茶葉の特徴を引き出す製法ではないんです。
- 大井
- ということは、その産地のその茶葉に合わせて一番いい製法を農園や生産者の方が考えて作っているのが、今扱われているインドとスリランカの産地ということですね。

- 大井
- “季節の特徴が表れている紅茶”も重視されているということですが、それはどのようなものでしょうか。
- 水野さん
- 例えばスリランカの標高の高い産地では、一年を通して茶葉は成長しますが、季節風の吹くタイミングによって香りがぐっとよくなります。それが季節であり旬だと思っています。
- 大井
- 季節風が吹くことでどうして香りがよくなるのでしょうか?
- 水野さん
- 基本的に紅茶の旬はドライシーズンが多いんですね。乾季になると、お茶の木が生き残るために自分で栄養を蓄えようとするので、その力が味やクオリティに表れてくるようです。果物やワインに使うブドウも、雨の多い時よりも、乾いた時期のほうが果物の旨みが凝縮されると聞いたことがありますね。
- 大井
- インドとスリランカではドライシーズンは違うのでしょうか?
- 水野さん
- はい。インドで代表的な産地のダージリンは、春は3月から4月の頭、夏は5月の終わりから6月の前半、秋は10月から11月。その3回シーズンが旬で、それぞれ季節の特徴が表れた紅茶が作られます。
- 大井
- ダージリンと言えば、“ファーストフラッシュ”や“セカンドフラッシュ”という言葉をカフェのメニュー表で見たことがあります。
- 水野さん
- そうですね。ダージリンは収穫時期に合わせて春がファーストフラッシュ、夏がセカンドフラッシュ、秋がオータムナル、オータムフラッシュと呼ばれています。
- 大井
- どれが一番美味しい……というのはあるのですか?
- 水野さん
- “美味しい”というのは主観的な判断基準だと思うので、それぞれの好みだと思いますが、ダージリンでは特徴となる香りや味の深みが一番出るのがセカンドフラッシュだと言われていて、一年で最も高値で取引されています。アッサムもそうですね。
- この続きはVol.4の「“産地の個性”がでている紅茶とは」で!次回の公開は1月27日(金)です!どうぞお楽しみに!
注目トピックス
新着の投稿
新着まとめ
地域を選択する